自己資金なしから日本政策金融公庫の創業融資を受けるための5つの方法

起業を考えておられる方が最初に悩まれるのが開業資金をどうやって集めようかということ。
その点、日本政策金融公庫の新創業融資は非常に魅力的です。
創業予定の、あるいは創業したてで実績がなく担保も持たない方でも借りられる起業家の味方です。
創業融資を借りるためにはいくつかの条件がありますが、その中でにとても重要な「自己資金の要件」というものがあります。
創業融資のホームページには、「創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方」、
との記載があり、借りたい金額の10分の1以上の「自己資金」がないと、申し込みが出来ないことになっています。
では、自己資金をそんなにないけれど、創業融資を借りたい、という方はどうすればいいのでしょうか?
ここでは、自己資金なし、という人でも創業融資が受けられるようになる方法をご紹介します。
自己資金とは何か
それでは、まず申し込み要件にある「自己資金」とはどういったものでしょうか。
例えば、それは、これまでの生活の中で貯めてきたお金で、自分が開業する事業のために自由に使える資金のことをいいます。
政策公庫の申し込みをすると、この自己資金の確認があります。
面談の日には預金通帳を持って行って担当者に確認してもらうことになります。この時、通帳は原本が必要でコピーではいけません。
ここで、自己資金がいくらあるのか、これまでどのように貯めてきたのか、などの確認がしっかりと行われます。
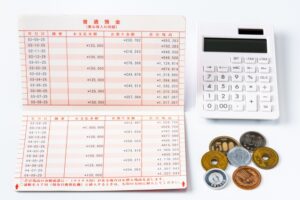
自己資金については、預貯金の残高だけを見て足りないなと思っていても、以外のなものが自己資金として見てもらえたりしますし、逆に自己資金に含めていけないものもあります。
生計が同じ家族の預貯金であったり保険の解約返戻金の予定額、既に事業のために支払ってしまった設備や敷金の代金なども含めることが出来ます。
自己資金に含めることが出来るものは何か?については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
自分の身の回りのもので、自己資金になりそうなものがないかどうか、まずは探しみてください。
自己資金なしでも創業融資に申し込みが出来る要件とは
それでも自己資金が足りない、あるいはまったくないという場合はどうすればよいのでしょうか。
実は日本政策金融公庫の新創業融資には、「自己資金の要件を満たすものとする要件」というものがあり、この要件を満たすことで自己資金なしでも申し込みが出来るようになっています。
その要件はこちらになります。
(1)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(2)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
2.大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、
その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
3.産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
4.民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
5.技術・ノウハウ等に新規性が見られる方
6.新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、
商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の
黒字化が見込める方
7.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の
適用予定の方
~日本政策金融公庫 新創業融資制度の「自己資金の要件を満たすものとする要件」より~
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/yoken_shinsogyo.html
「1.」については、開業する業種と同じ業種経験が、連続でなくても合計6年以上あればクリア出来ます。

「3.」についてはお住まいの市区町村でセミナー等が開催されていないか探してみてはいかがでしょうか。参加することで創業に必要な様々な知識が得られるほか、会社設立時の登録免許税が免除されるなど、いろいろなメリットがあります。
「7.」は法人に限定されてしまいますが、税理士に依頼すれば要件にあった会計処理で決算書を作成してくれます。
これらの要件をクリアすることで創業融資に自己資金なしで申し込むことができます。
創業融資の審査に受けるかどうかは別問題

しかし、自己資金なしでも申し込みが出来るというだけであって、実際に融資が受けられるかどうか別問題となります。
では、どれくらいの自己資金があれば審査が受かり、創業融資が借りられるのかというと・・・
日本政策金融公庫の創業計画Q&Aのホームページにヒントとなるものが書かれています。
Q 自己資金はどれくらいあればよいですか?
A「一概には言えませんが、「2013年度新規開業実態調査」(日本政策金融公庫 総合研究所調べ)によると、創業資金総額に占める自己資金の割合は27%となっています。自己資金以外には、金融機関等からの借入金が61%、親族が6%、その他が6%となっています。
事業が軌道に乗り資金繰りが安定するまでにはどうしても時間がかかります。借入金の返済や予想外の出費で資金繰りが苦しくなるなど、さまざまな問題が起こります。万一の時に備えて、数カ月分の経費相当分はとっておくなど、ゆとりを持った創業の資金計画をたてることが大切です。」
はっきりと明言していませんが、3割ぐらいは必要です、ということを示唆しているのではないでしょうか。
実際に日本政策金融公庫の複数の人間に問い合わせたところ、ほとんど全員が「3割ぐらいは用意しておいてほしい」と答えたという調査結果もあります。
国の政策運営上、起業・創業を増やす目的にのために従来と比べて自己資金要件を緩和する方向となっています。
しかし、政策公庫が持っている膨大なデータからすると、3割程度の自己資金が準備出来ていない起業については失敗する確率が高くなってしまうという予測から、内部の審査は厳しくなっているのでしょう。
事業計画書の作りこみが良く、起業当初から顧客がついているような特別なケースでもないかぎり、借りたい金額の3分の1ぐらいは持っていないと、創業融資を受けることが出来ないのです。
自己資金なしから創業融資が受けられるようになるための5つの方法
自己資金なしのままで創業融資を受けるのは非常に厳しく、なんとしても自己資金を増やしていかないといけません。
創業融資の審査が有利になるように、必要な自己資金を増やす方法を5つピックアップしてみましょう。
①親や親戚から贈与を受ける
起業を目指していたものの自己資金が不足していた方の中には、親や親戚に頼み込んで資金援助を受けて開業に踏みられる方もおられます。
こちらは純粋に自分が貯めてきた自己資金というわけではありませんが、手持ち資金が増えることで審査に有利に働きます。
しかし、ここで気を付けなければならないのが、必ず「贈与」、つまり貰ったという形でないといけません。
これを「借りてきた」という場合、例えば事業が軌道にのったら返すからという約束で一時的に借りてきような場合では、自己資金としては見てもらえません。
創業計画書にはわざわざ「親、兄弟、知人、友人等からの借入」という記入欄があり、貰ったお金と借りたお金を区分するようにしています。
この区分が重要ですので、贈与契約書などを作成して贈与であることをはっきりさせておきましょう。
また貰う方法も現金でもらうのではなく、通帳振込などでいつ誰から貰ったのかがはっきり証拠に残るようにしておきまししょう。
お金の出所が分からないようだと「みせ金」との区別がつかないためです。
なお親や親戚から開業資金として使うお金を借りること自体は問題ありません。経費の一部を親・親戚からの借入でまかなうことで、起業をスムーズに進めることが出来るのなら、一つの手段といえます。
しかし、いつどのように返済するのかについては説明を求められることになります。
返済のために資金繰りを圧迫するようなことでは、公庫への返済にも疑念をもたれ審査にマイナスとなってしまいますので、そのような影響がないことを返済計画を示してしっかりと説明できるようにしておきましょう。
②共同経営者を集め出資を募る
法人を設立し、事業を共に行う共同経営者を集めることで、その共同経営者から出資を募って自己資金を増やすこともできます。
共同で事業を行うことで、役割分担ができてビジネスの幅を広げることも可能にもなります。
しかし一方で、経営の方向性や利益の分配などでトラブルとなるデメリットもあります。
ここで気をつけないといけないことは、あたなが51%以上を出資する必要があります。
株式会社や合同会社は出資比率が51%以上の人間が、その会社の実質的支配者となります。
そのため会社の資本金の51%以上をあたなの自己資金から出さなければなりません。
そうでないと、その会社はあなたのものでないとみなされて、創業融資を受けるために代理を立てているのではないかと見られてしまうからです。
③担保を設定する
日本政策金融公庫の創業融資制度は、無担保・無保証となっていますが、あえて担保を付けることで、融資金額を増やしたり審査の可能性を上げることがができます。
担保としての価値がないものや値段の査定が難しいもの、例えば古びた家屋だったり一山いくらの土地だったりすると担保には出来ません。
評価金額の高い不動産をお持ちの人はこちらの方法が効果的になります。
なお、担保を付けられるのは、住宅ローンなどの担保がついていない不動産に限られますし、共有物件となっている場合には、その共有相手の承諾もいることになります。
④現物出資を行う
法人を設立して、車やパソコンなどの、お持ちの資産をその法人に提供することを現物出資といいます。
この現物出資を行うことも一つの手段になります。
この場合、出資した資産の値段が自己資金として見てもらえます。
値段については、客観的な資料が必要になります。例えば車なら、中古車の買い取り査定の見積もりなどが必要です。
ただし、事業に必要なものであることが条件になります。価値があるからといっても趣味の品などは対象になりません。
⑤半年~1年とかけてコツコツと貯める
最後になりますが半年~1年程度かけてコツコツと貯めることが、やはり一番確実な方法といえます。
開業を目指しはじめたばかりの時期に自分が理想とするような物件が出た場合、このチャンスを逃したくないと焦る気持ちはわかります。
しかし、自己資金がないということは準備が出来ていないということでもあります。
日々の経費を削減して資金繰りを良くしていくことは、これから事業を始めるうえでも大事なことにもなりますし、副業として始めておくことが出来るのであれば、お金も貯めれますし業務経験として有利になります。創業計画書も作成しやすくなるでしょう。
最低でも10分の1を資金を貯められれば希望はあります。例えば1000万円が必要な場合で1年後に100万円を貯めることを目指すなら、1ヶ月で8万円、頑張ればなんとかならない金額ではありません。

起業を目指してコツコツと貯めてきた記録が残っている通帳は、公庫の人からも高い評価を受けるでしょう。
そうして準備が整ったときに「いいな」と思う物件に出会えたら、それこそ選ぶ価値のある物件で、その時こそ起業の時期ではないでしょうか。
自己資金が10分の1しかなくても創業融資を受けられるのか?
創業融資の自己資金は3割程度が必要と言われています。
だからと言って、
「自己資金が10分の1しかない場合は絶対に融資はしてもらえないのか?」
と言われると、そんなことはありません。
創業融資で10分の1しか自己資金がなくても、希望額の融資を受けられたという事例はいくらでもあります。
確かに3割程度の資金を用意できないと、成功率は低くなりますし、融資額を減額されることもあります。
ですが、自己資金が少なくても「しっかりとした創業計画」を作ることが出来れば、借りられることはあります。
創業計画書の内容について確かな根拠を示して納得してもらうことが出来れば、この事業計画だったら返済に問題ない、との判断で融資を受けることは可能になります。
しかし、創業計画書を作成した経験のない起業家が、「しっかりした創業計画」を作成するのはとても難しいことでしょう。
「頑張って10分の1まで貯めたからなんとかしてほしい」「3分の1までには自己資金が不足しているが、どうしても今、起業したい」という場合は、お近くの創業融資の専門家に相談してみてはどうでしょうか。
創業融資の獲得を成功させるために、準備をしっかりと
いかがでしたでしょうか。
起業を成功させるためには、十分な開業資金・運転資金がが必要不可欠です。
創業融資を借りることが出来れば、起業してからの資金繰りにも安心感が持てますし、事業を進めていくうえでも心の余裕が持てるようになります。
自己資金は1円でも多ければ多いほど、創業融資で借りられる金額も成功率も上がります。
こちらの記事が参考になれば幸いです。
創業融資は1度申し込みをして落ちてしまうと再び申し込むことが非常に難しくなりますので、
十分な融資を受けられるようにあらかじめ準備をしておくことをお勧めします。


